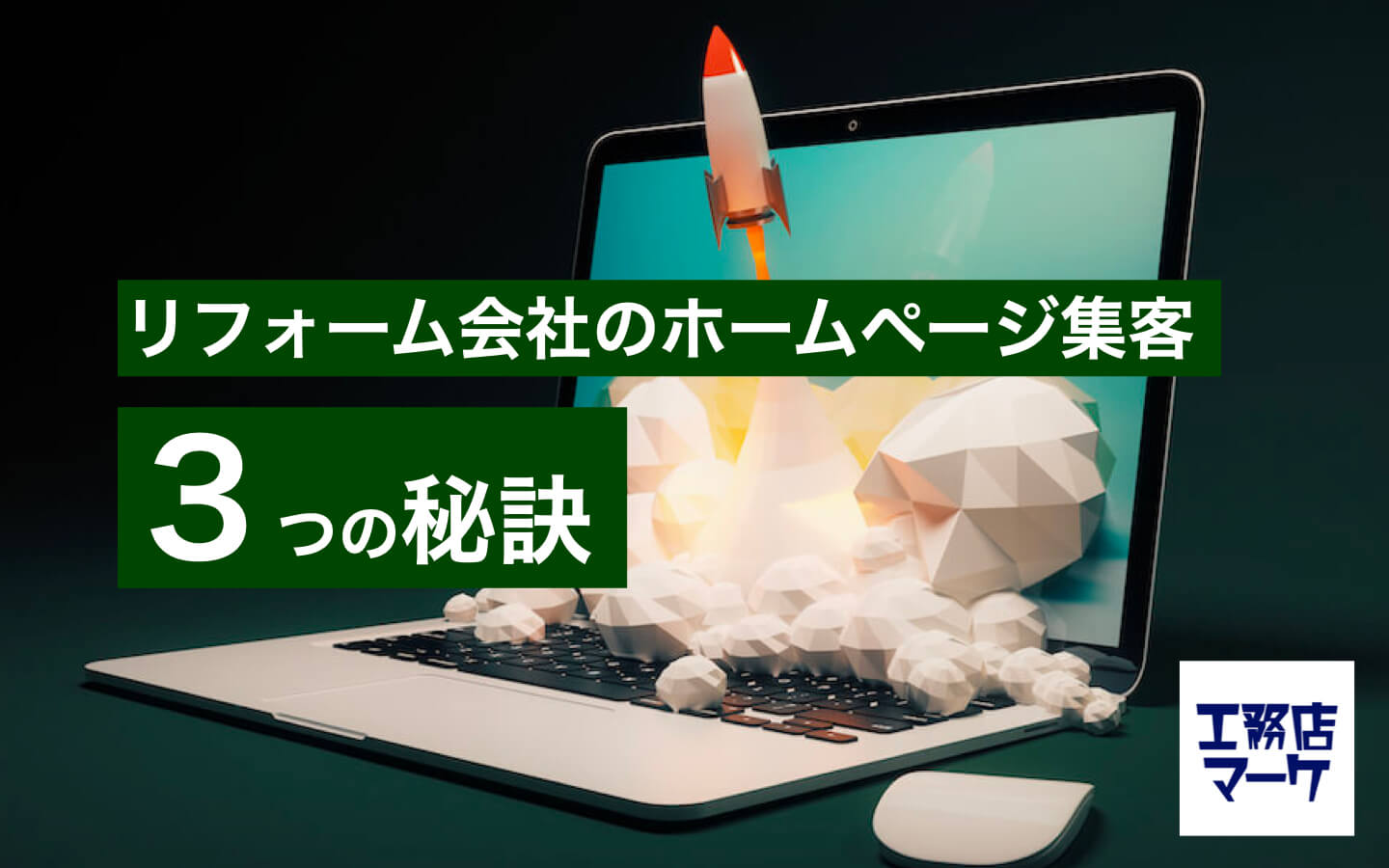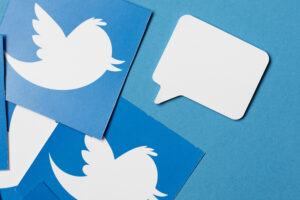工務店の集客の要はSNSになりつつあります。本コンテンツでは、工務店のSNS活用術について解説します。
- Instagram、YouTube、LINEの活用のポイント
- SNS投稿のネタの出し方
- 反響に繋げる動線設計
本コンテンツの学習にかかる目安時間は10分〜15分程度です。
本コンテンツの目次
工務店の集客にSNSは「必須」になった
かつて、工務店の集客といえばチラシや紹介が中心でした。しかし、2020年代に入り、SNSの活用が集客の要となりつつあります。これは都市部だけでなく、地方の小規模な工務店にも当てはまる傾向です。
住宅検討者の情報収集行動が変わった
住宅の購入を検討している人の多くが、まずInstagramやYouTubeで「施工事例」や「ルームツアー」などを探す時代です。検索窓に「#注文住宅 間取り」「#平屋 24坪」「#施工事例 ○○市」などのキーワードを入力し、SNS上で情報収集するのが当たり前になっています。
特に以下のような層は、SNSを情報源として積極的に活用しています。
- 20代〜40代の共働き夫婦
- 自由度のある住宅を希望する人
- 住宅展示場に足を運ぶ前に「自分好みの家」を明確にしたい人
このような顧客は「いいな」と思う工務店のSNS投稿を見て、公式サイトや資料請求へ進みます。SNSは最初の接点を生む入り口として、今や欠かせない存在となっているのです。
SNS経由での問い合わせ・成約も増加中
さらに、SNSは“情報収集のためのツール”を超えて、実際の問い合わせ・成約につながるチャネルにもなっています。たとえばInstagramのDMやLINE公式アカウントを通じて、
- 資料請求を希望
- 完成見学会への参加予約
- モデルハウスの来場申込み
といったアクションが日常的に起きています。
工務店の中には「SNSで集客なんて、都会の大手だけがやってる話でしょ」と感じている方もいるかもしれません。しかし、実際は地域密着型の小さな工務店ほど“人柄”や“施工のこだわり”をダイレクトに伝えられるSNSとの相性が良いのです。
次章では、それぞれのSNS(Instagram・YouTube・LINE)の特性と、工務店としての活用ポイントを詳しく見ていきましょう。
【2025年注目】各SNSの特徴と活用法
工務店がSNSを活用する際、重要なのは「どのSNSに、どの目的で取り組むか」を明確にすることです。ただ何となく投稿を続けるだけでは、反響にはつながりません。ここでは、特に注目すべき3つのSNS――Instagram・YouTube・LINE公式アカウントについて、それぞれの特徴と活用法を解説します。
Instagram:施工事例の魅せ方が集客力を左右する
Instagramは、視覚的な印象がすべての起点となるSNSです。住宅業界においては、施工事例やデザインセンスを伝える“ショーケース”として、極めて有効なメディアです。
Instagram活用のポイント
ビジュアル重視
写真のクオリティが重要です。自然光で撮影されたリビングやキッチン、素材感の伝わる床や壁などが人気です。
ハッシュタグ活用
「#平屋」「#ルームツアー」「#○○市の工務店」など、地域名や住宅タイプのタグを使い分けましょう。
投稿の一貫性
フィードの世界観を統一することで、ブランディングに直結します。
Instagramの人気の投稿ジャンル
完成物件のルームツアー風写真(リールでも可)や施主の声(インタビュー形式)といった実際に建てた事例や生の声が人気です。リノベーションにおいてはビフォーアフターも人気の投稿ジャンルになります。
Instagramは、いわば“指名検索前の種まきです。「この工務店、いいかも」と思わせる“きっかけづくり”に最適なSNSです。
参考:【2024年7月更新】Instagramの使い方 工務店の活用事例19選
YouTube:ルームツアーと職人密着で“ファン”を生む
YouTubeは、視聴時間の長さが大きな強みです。Instagramよりも深く、“その工務店の価値観や仕事ぶり”を伝えることができます。
YouTube活用のポイント
ルームツアー動画
家全体の雰囲気、間取り、住み心地などを紹介するコンテンツは特に人気です。是非とも投稿したいジャンルになります。
社長や設計士現場社員の出演
構造や施工精度へのこだわりを見せることで、他社との差別化が可能です。また実際に設計等に関わる社員の話し方・考え方を知ってもらうことで、信頼感が生まれます。
YouTubeの動画のテーマ例
「○○坪・○○万円の平屋ルームツアー」、「現場監督の1日に密着|○○工務店の家づくり」「施主様インタビュー|決め手は“提案力”でした」といったコンテンツが考えられます。
ルームツアーは動画の尺が長い分詳しく紹介ができる点がポイントです。また、社員や施主の生の声は動画で伝わる要素が多いため、YouTubeに向いたコンテンツといえます。
YouTubeは、投稿のハードルが高いと感じられるかもしれません。しかし、一本の良質な動画が数年にわたって集客効果を持ち続けるという、極めてコスパの良い資産型メディアでもあります。
LINE公式アカウント:問合せから成約までつなぐ仕組み
InstagramやYouTubeで「いいな」と思ってもらった見込み客を、“手の届く関係”に変えるのがLINEの役割です。
LINE活用のポイント
自動返信とチャット対応の使い分け
資料請求やイベント予約は自動化、具体的な相談には有人対応を行うことで効率的に対応できます。
定期配信・ステップ配信の活用
完成見学会のお知らせや土地情報などを、定期配信で月1〜2回配信することでリード顧客との関係性を維持できます。また、登録直後の1週間で「施工事例→会社紹介→見学会案内」と自動で配信するステップ配信の設計も効果的です。
LINE導入時の注意点
LINE登録までの導線設計(InstagramプロフィールやWebサイトに誘導)を工夫しましょう。ユーザーに「営業される」印象を与えないよう、あくまで情報提供や親切な相談窓口としての立ち位置を意識することが大切です。
LINE公式アカウントは、“反響を成果につなげるための受け皿”として極めて重要です。
次章では、これらSNSを継続して運用するための仕組みや、ネタ出しに困らない考え方を解説します。
工務店がSNSに取り組む際、「ネタがない」「続かない」と悩むのはごく自然なこと。ここを乗り越える具体策を見ていきましょう。
工務店のSNS運用のコツ|継続できるネタ出しと投稿の仕組み化
SNS活用を始めた工務店が直面しやすい壁――それが「ネタが続かない」「更新が止まる」という問題です。どれだけ魅力的な投稿をしていても、継続できなければ効果は出ません。この章では、実際の工務店が実践している“無理なく続けるSNS運用のコツ”を紹介します。
ネタは「現場」と「お客様」の中にある
SNS投稿のネタに困ったときは、あらためて“日々の業務”に目を向けてください。以下のような日常の一コマこそが、ユーザーにとっては新鮮で、信頼感を生むコンテンツになります。
ネタ出しのヒント例
以下のような内容がSNS投稿のネタにつながります。
- 現場の進捗報告(上棟式、クロス貼り、外構工事など)
- 現場スタッフや職人の紹介・仕事風景
- 施主様との打ち合わせ風景(イラストや図面紹介も可)
- 社長や設計士の「間取りに込めた想い」
- 完成物件の撮影舞台裏
- 質問の多い内容のQ&A(「土地探しのポイント」「断熱って必要?」など)
ポイントは、「この情報は出していいのか?」と悩まず、まずは“伝える前提”で写真・動画を日常的にストックすることです。
投稿パターンを決めて“思考の手間”を減らす
SNS運用を継続するには、「考えなくても回せる仕組み化」がカギです。おすすめなのが、曜日別・ジャンル別の投稿パターンをあらかじめ決めてしまう方法です。
【例:Instagramの投稿設計パターン(週4回)】
| 曜日 | 投稿内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 月曜 | 完成物件紹介 | 写真5〜8枚+ハッシュタグ |
| 水曜 | 社員・職人の日常 | リールやストーリーも◎ |
| 金曜 | お客様の声・Q&A | カルーセル投稿も可 |
| 土曜 | ルームツアー風リール | 動画編集アプリ活用 |
これにより、「今日は何を投稿しよう…」という思考時間をゼロに近づけることができます。
運用担当の負担を減らす“分業化”も検討を
「SNSは広報担当が1人で回すもの」と考えられがちですが、長期運用を見据えるなら社内での“ゆるやかな分業体制”が理想です。
【分業の例】
- 現場担当者が写真・動画を社内チャットに投稿
- 設計士がストーリー用のコメントを用意
- 広報担当がそれらをまとめてSNS投稿に落とし込む
また、月に1度「SNSネタ共有会」や「現場ストック確認会」を設けることで、投稿素材が常にある状態をつくることができます。
投稿本数より「継続」が最大の武器
SNSでは「毎日投稿しないと伸びない」というプレッシャーを感じがちですが、重要なのは“質”と“継続性”です。週に2回でも、2年間続けていれば100本を超える投稿資産になります毎回の投稿が「住宅検討層」の検索・比較検討の中で生きてきます
SNS上で「この工務店、ずっと真面目に発信してる」と認識されることが、最大の信頼構築につながります
継続を可能にするには、「ネタ出し」「投稿設計」「分業体制」「仕組み化」の4つがそろってこそ。次章では、こうして継続的に発信してきたSNSを、どうやってWebサイトや広告と連携させて、反響につなげるかを解説します。
反響につなげる!SNSとWebサイト・広告の連携術
SNSで興味を持ってくれた見込み客を、「実際の問い合わせ」や「資料請求」へと導くためには、連携の設計が不可欠です。SNS単体で完結させるのではなく、Webサイトや広告と組み合わせて「導線設計」を最適化することで、反響率を大きく高めることができます。
SNSは“最初の接点”にすぎない
InstagramやYouTubeの投稿を見て「この工務店、気になる」と思った人が、いきなり問い合わせをすることは稀です。実際の行動としては、多くの人が次のようなフローを踏みます:
- SNS投稿で存在を知る
- プロフィールのリンクからWebサイトにアクセス
- 会社概要・施工事例・スタッフ紹介・価格帯をチェック
- LINE登録・資料請求・イベント予約などのアクションへ
つまり、SNSは“きっかけ”づくり、Webサイトは“判断材料”、LINEや広告は“コンバージョン(反響)”を促す導線です。それぞれの役割を分けて考えることが重要です。
Instagram・YouTubeからWebサイトへ誘導するコツ
SNSのプロフィールや投稿からWebサイトにスムーズに誘導するためには、「導線のわかりやすさ」と「行動喚起の言葉(CTA)」がカギです。
導線設計のポイント
Instagramは、プロフィールに「リンクまとめ(Linktree等)」を設置し、サイト・資料請求・LINEなどにジャンプできるようにすると良いでしょう。YouTubeは、概要欄に、施工事例ページや見学会ページのURLを明記することをお勧めします。
また、誘導したいLPがある場合、投稿や動画内に「詳しくはプロフィールのリンクから」など明確なCTAを入れることも重要です。
見込み客が“次にとるべき行動”を迷わないように設計することが、反響率を左右します。
SNS × 広告で「指名検索される前に出会う」
SNSを運用していても「なかなか新規の流入が増えない」と感じる場合は、SNSと広告を組み合わせることで、より多くの潜在顧客にアプローチできます。
おすすめの広告活用例
以下のように広告を使ってSNSを拡散する方法が考えられます。
- Instagram投稿の一部をリール広告として配信
- YouTube動画をP-MAXキャンペーンやディスカバリー広告で露出
- LINE広告で「資料請求キャンペーン」や「完成見学会告知」
SNS上の投稿を「オーガニック(自然投稿)」だけで拡散しようとすると限界があります。優秀な投稿は、広告でさらに拡張することで“安定した集客チャネル”に変化します。
SNSとLINE公式アカウントを連携させる
SNSで興味を持ったユーザーに、LINEで「直接つながってもらう」ことで、リスト化とコミュニケーションが可能になります。
たとえば、InstagramプロフィールリンクからLINE登録へむすびつけ、登録直後に自動返信で「施工事例カタログ」などを送付、以降、見学会案内や家づくりコラムを定期配信といった流れを仕組み化することで、SNSで生まれた関心を、中長期の関係構築へとつなげられます。
SNSは“単体”ではなく“導線全体”で設計する
繰り返しになりますが、SNSは「認知」「共感」「第一印象」をつくる場であり、実際の成約につなげるにはWebサイトやLINE、広告と組み合わせた“設計された動線”が不可欠です。
SNS投稿 → Webサイト閲覧 → LINE登録・資料請求 → 見学会参加 → 成約
という流れを意識して、運用体制を整えましょう。この“顧客化の流れ”を社内でも共有し、投稿や広告の設計を見直していくことが、SNSを「集客資産」に変える近道です。
最初の一歩は「1投稿から」でもOK
SNS運用というと、「動画編集ができない」「ネタがない」「忙しくて時間が取れない」といった不安を抱える方も多いでしょう。
しかし、成功している工務店も、最初は“スマホで撮った1枚の写真”から始めています。
最も大事なのは、「完璧を目指すより、まず始めて、続けること」。1本の投稿が、数ヶ月後に資料請求を生むこともあります何気ない現場写真が、他社との違いを伝える武器になります。
続けて発信していることで、見込み客は安心感を抱きます。SNSの活用は、“即効性”よりも“持続性”の勝負。地域の工務店こそ、顔が見える発信で共感を生み、じわじわとファンを増やしていくことができます。