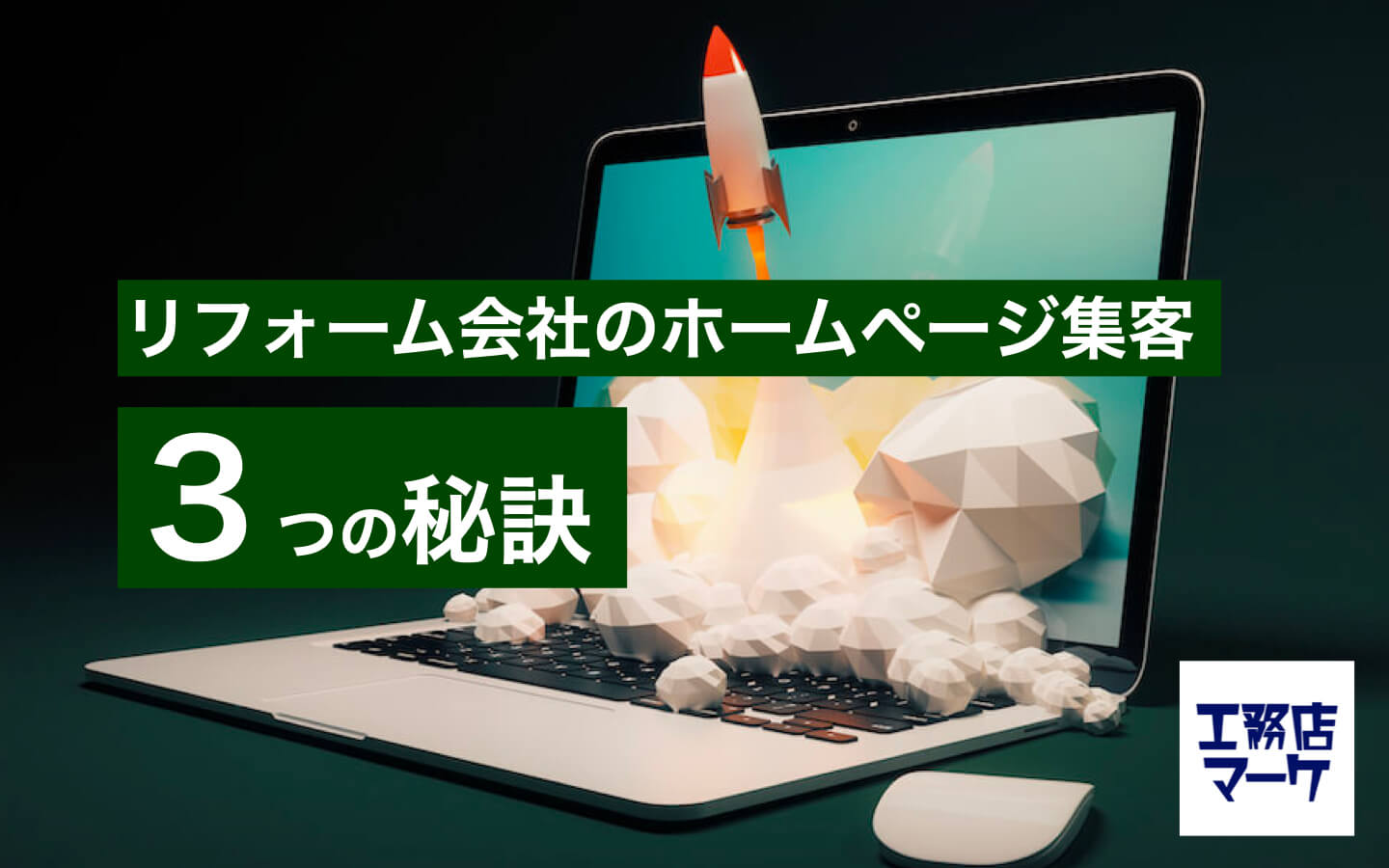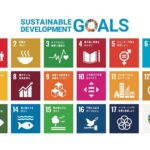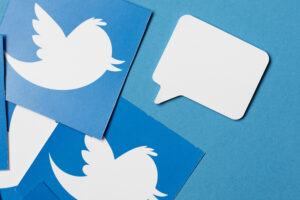工務店が地域で顧客に選ばれるためには、時代に合った複数の集客チャネルを活用し、認知獲得から問い合わせまでの導線を丁寧に設計することが大切です。
本記事では、集客に効果的な4つの集客方法をご紹介します。
- 工務店が効果的に集客するための基本施策(ホームページ、SNS、MEO、ネット広告)の具体的な内容と実践ポイント
- 施策の優先順位の考え方
本コンテンツの学習にかかる目安時間は5分〜10分程度です。
本コンテンツの目次
ホームページの作成
まず取り組みたいのが、ホームページの整備です。工務店の強みや施工実績を的確に伝えることで信頼感を醸成し、問い合わせにつなげる役割を果たします。ホームページを作成する際は、GoogleやYahoo!での検索順位を上げるためのSEO対策と、ホームページに訪れたユーザーが資料請求などの行動をするように促すCVR向上の2つを意識する必要があります。
SEO対策
ホームページ作成時には、GoogleやYahoo!の検索で上位に表示されるようにするためのSEO対策が必要です。SEOは無料で流入を確保できるうえに、一度上位表示されると継続的な効果が見込め、ホームページの存在自体が資産になります。
SEO対策するキーワードの選び方
対策するキーワードは「エリア+注文住宅」や「エリア+〇〇住宅(例:自然素材、ZEH、平屋など)」といった地域掛け合わせのキーワードがおすすめです。
「注文住宅」といったビッグキーワードは、大手ハウスメーカーやSUUMOなどのプラットフォームが押さえており上位表示が難しいことに加え、注文住宅やリフォームは地域性がある事業であるためです。検索ユーザーの多くは地名とニーズを組み合わせて調べるため、地域密着型のキーワード戦略が有効です。
SEO対策のための施策
SEO対策では、狙ったキーワードで検索されやすくなるよう、各ページに情報を盛り込むことが必要です。
たとえば「XX市+平屋」というキーワードを狙う場合、ページ上に「XX市」「平屋」というキーワードを明記し、関連するコンテンツを作成しましょう。具体的には、XX市の平屋の施工事例紹介や平屋に関する解説記事などがこれに該当します。
ユーザーが検索する際にどのような情報を求めているかを想定して、必要なコンテンツを用意しましょう。
参考:【2023年10月更新】工務店向けSEO対策 基礎講座
CVR向上施策
ホームページは、ユーザーが訪問しただけでは意味がありません。問い合わせや資料請求といったCV(コンバージョン)につながって初めて成果となります。
そのため、問い合わせや資料請求への導線を明確に設置しましょう。ページ下部だけでなく、スマホでの閲覧を考慮し、画面内で常に問い合わせできるような導線設計が成果を高めます。
さらに、ユーザーに「この工務店に頼みたい」と思ってもらえるような情報提供が必要です。自社の強みや理念を明確に伝え、施工事例を豊富に掲載することで、安心して問い合わせができるホームページになります。写真だけでなく、工夫したポイントやお施主様の声も添えることで、より信頼性が増します。
SNSの運用
SNSは、工務店を探しているユーザーと自然に接点を持つための有効なツールです。とくにInstagramやYouTubeは、住宅を検討している層に情報を届けやすい媒体です。
工務店を探しているユーザーは、Instagramでも積極的に検索・情報収集を行います。そうしたユーザーにアプローチするには、まず魅力的な投稿を行うことが重要です。施工事例や工事中の様子、現場スタッフの紹介、建てる家のイメージなど、意思決定の助けとなる情報を継続的に発信しましょう。
リール機能を活用して、ルームツアー形式で詳しく紹介するのも効果的です。また、問い合わせにつながるようにCV導線も整備しておくことが必要です。
Instagramでは「#地域名+工務店」「#注文住宅アイデア」などのタグ検索が活発です。SEOと同様に、CVにつながるワードをタグに含めましょう。
YouTube
高額商品ほどYouTubeでの情報収集が活発で、注文住宅はその代表格です。動画主体のため、Instagramよりも詳細な情報を伝えられるのが特長です。
主な活用方法は、施工事例のルームツアー動画です。間取りや動線、素材の質感を紹介することで、文字や写真では伝えきれない魅力を発信できます。
動画は「再生回数」よりも「検討層に届いているか」が重要です。CVに繋がったかをアンケートなどで分析しながら、改善していきましょう。
MEO対策
MEO(Map Engine Optimization)とは、Googleマップ上での検索順位を上げる施策です。「地名+工務店」で検索するユーザーが地図情報から問い合わせ先を選ぶ傾向があるため、非常に重要なチャネルです。
Googleビジネスプロフィールを整備し、営業時間や施工エリア、施工写真、サービス内容を最新の状態に保ちましょう。定期的な更新も重要です。
また、口コミも意思決定に大きな影響を与えます。引き渡し後のタイミングなどで、施主にGoogleへの口コミ投稿を依頼し、投稿には丁寧に返信しましょう。信頼感の高いプロフィールが構築できます。
参考:工務店のMEO対策
インターネット広告の運用
すでに家づくりに関心のあるユーザーにアプローチするには、インターネット広告も効果的です。中でもリスティング広告(検索連動型広告)は、検討が進んでいるユーザーに直接リーチできるため、優先度が高い施策です。
リスティング広告
「〇〇市 注文住宅」など、明確な意図を持って検索しているユーザーに広告を表示できます。
ホームページでCVRを高める施策(LPO)と併せて運用すると効果的です。また、キーワードは定期的に見直し、成果が出ないものは除外、新しいキーワードを追加するなど運用の最適化も欠かせません。部分一致や拡張一致を活用し、検索ニーズを逃さないようにしましょう。
P-MAX
リスティング広告で一定の成果が出ている場合は、GoogleのP-MAX広告もおすすめです。検索・YouTube・ディスプレイなど複数の媒体に一括配信できるため、潜在層にも広くアプローチできます。
広告主としては、良質な画像や動画などの素材を用意し、配信精度を高めることが求められます。施工事例など自社の強みを活かしたクリエイティブを準備しましょう。
Instagram広告
Instagram広告は、検索ではなく「フィード上で出会う」ユーザーにアプローチできます。特に注文住宅やリフォームはビジュアルの印象が決め手になりやすいため、施工写真や動画による訴求が効果的です。
P-MAX同様、広告の成果はクリエイティブ次第です。効果的なクリエイティブを見つけて差し替えながら運用しましょう。
参考:【2024年2月更新】工務店のリスティング広告運用のポイント
複数の集客方法を組み合わせて最適化しよう
工務店集客にはチラシや住宅ポータルサイトの活用など、他にもさまざまな方法がありますが、本記事では特に効果の高い4つの施策を紹介しました。
重要なのは、費用対効果を正しく把握し、効果の薄い施策は中止、成果が出ている施策に集中投資していくことです。アンケートやヒアリングを通じて流入経路を把握し、施策の評価と改善を継続して行いましょう。
まずは、自社にとって取り組みやすい施策から一歩踏み出してみてください。地道な実践の積み重ねが、信頼されるブランドづくりと安定した集客につながっていきます。